トラックドライバーに必要な免許とは?それぞれの免許の取得条件・流れなど解説!

トラックドライバーとして働くためには、車両を運転するための免許が必須です。ただし、トラックといってもさまざまな種類があります。大きさによって運転できる免許が異なるため、希望する仕事で使われているトラックの運転に必要な免許を持っていなければなりません。この記事では、トラックドライバーに必要な免許について詳しく解説します。
トラックの運転に必要な免許とは?
トラックを運転するためには免許が必要です。免許の種類は複数あり、それぞれの免許で運転できる車両の種類も定められています。トラックの運転に必要な免許は、普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許の4つです。
免許によって就ける仕事にも違いがでてくるため、ここからはトラックドライバーにとって大切な4つの免許をそれぞれ解説します。*1
大型免許
大型免許を所有していれば大型自動車はもちろん、中型自動車や準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車および、原動機付自転車の運転が可能です。トラックの運転に必要な免許のなかでは、最も運転できる車両の種類が多くなっています。大型の車両はもちろん、普通自動車などの小型の車両まで幅広くカバーしているため、さまざまな現場で使える免許です。
ただし、特殊車両の運転については小型特殊自動車は可能ですが、大型特殊自動車は含まれていません。また、原動機付自転車の運転もできますが、それよりも大きい二輪車を運転するには普通二輪免許や大型二輪免許が必要です。
中型免許
中型免許で運転ができるのは、中型自動車と準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車および、原動機付自転車です。中型免許では大型自動車は運転できませんが、それよりも小さい中型自動車から普通自動車までは運転できます。大型免許と同様に、小型特殊自動車と原動機付自転車の運転も可能です。
中型免許は2007年の道路交通法の改正で作られた免許で4トントラックなど運転できる車両は多く、実際にさまざまな業界で使われています。
大型免許に比べると運転できる車両の種類が少なくなるものの、中型免許を取得していればかなり仕事の幅は広がるでしょう。
準中型免許
準中型免許は、中型免許と普通免許の中間にあたる免許です。詳細な理由は以降の段落で後述しますが、主に運送業界の人材不足の解消や交通事故の削減を目的として、2017年の道路交通法改正時に新設されました。運転できるのは準中型自動車と普通自動車、小型特殊自動車および、原動機付自転車です。
大型免許や中型免許のような大きい車両の運転はできませんが、普通免許に比べて運転できる車両の幅が広く、準中型免許を取得することで活躍できる場が広がります。準中型免許は、普通免許と同様に18歳になれば免許の取得が可能です。
普通免許
普通免許で運転できるのは、普通自動車と小型特殊自動車および、原動機付自転車です。一般的に「自動車の免許を取る」といえば、まずこの普通免許を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。レジャーや通勤にも使えるので、トラックドライバーとして従事する目的でなくても持っている人が多い免許です。
ただし、普通免許には自家用として公道を走ることができる第一種免許と、タクシーなどのように旅客を乗せて営業運転するための第二種免許があります。タクシー運転手などの職業に就くためには、第一種免許取得後、条件を満たしたうえで第二種免許を別に取らなければなりません。
普通免許でもトラック運転手になれる?
結論からいうと、普通免許でもトラックの運転は可能です。ただ、もちろん大型免許や中型免許、準中型免許で運転できる大きさのトラックに乗れるわけではありません。また、法改正によって2007年に中型免許、2017年に準中型免許が新設されたことにより、段階的に普通免許で運転できる車両の範囲も変わりました。
普通免許は取得した時期によって運転できる車両の総重量や最大積載量、乗車定員数などが異なるため、以降の段落で詳しく解説します。*2
2007年6月1日までに普通免許を取得している人
2007年6月1日までに普通免許を取得した人の場合、「8トン限定中型免許」という扱いになり、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員数10人以下の大きさの車両まで運転が可能です。
2007年6月1日に道路交通法が改正される以前は第二種免許やけん引免許を除くと、自動車免許の区分が大型免許と普通免許の2種類しかありませんでした。現在のように大型免許と普通免許の間に中型免許や準中型免許がなかった分、普通免許で運転できる車両の範囲が広く取られていたのが特徴です。そのため、2023年時点で普通免許を所有している人のなかでは、もっとも幅広い大きさのトラックを運転できます。
2007年6月2日から2017年3月11日に免許を取得した人
2007年6月2日から、2017年3月11日までの間に普通免許を取得した人の場合は、「5トン限定準中型免許」という扱いになり、車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員数10人以下の車両の運転が可能です。2007年に中型免許の制度が導入されたことで、それまでは車両総重量が8トン、最大積載量が5トン未満の車両は運転できていましたが、それぞれ5トン、3トンに引き下げられています。乗車定員数は2007年6月1日までに普通免許を取得した人と同じです。
2007年6月1日以前に普通免許を取得した人よりは運転できる車両の範囲は小さくなったものの、2017年の準中型免許新設以降に普通免許を取得した人よりは幅広い車両に対応できます。
2017年3月12日以降に免許を取得した人
2017年3月12日以降に普通免許を取得した人は、運転できる車両の範囲が車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満、乗車定員数10人以下となっています。乗車定員数は変わりませんが、中型免許と普通免許の間に準中型免許が新設されたことで、さらに普通免許で運転できるトラックの大きさが小さくなりました。
先述したとおり、準中型免許の制度が導入される以前に普通免許を取得した人は、一部の中型自動車や準中型自動車の運転が可能です。しかし、2017年3月12日以降に免許を取得した人が運転できるのは普通自動車だけです。
2017年に新設!準中型免許

2017年に準中型免許が新設された背景には、運送業界の慢性的な人材不足と多発するドライバーによる交通事故という2つの懸念事項がありました。そこで人材不足解消に向け、18歳で取得が可能な準中型免許を新設することで、若年層が運送業界で活躍できる仕組みを作りました。
また、従来の普通免許では準中型自動車や中型自動車の一部が運転可能だったものの、実際には普通自動車以外の車両で教習を受けていない人も多くいました。慣れない車両の運転で交通事故が起こりやすくなる状況を減らすため、免許の区分もより細分化したものが「準中型免許」です。
準中型免許で乗れる車両は?
準中型免許で運転できる車両の総重量は3.5トン以上7.5トン未満、最大積載量は2トン以上4.5トン未満、乗車定員は10人以下です。具体的にはコンビニエンスストアの配送や単身者・夫婦二人暮らし程度の引っ越しに使われる2トントラック、サイズによりますがクレーンが架装されたユニック車、高所作業車などがあります。*3
ごみ収集に使われるパッカー車(いわゆるごみ収集車)も、2トントラックをベースに作られているため、2017年3月12日以降に取得した普通免許では運転できず、準中型免許の取得が必要です。
準中型免許は最大積載量が4.5トンまで大丈夫なものの、架装が付くことで車両総重量が7.5トン以上になることもあるため、乗れる車両は車両総重量と最大積載量を合わせて判断する必要があります。
準中型免許の受験資格は?
受験資格は免許の種類によって異なりますが、準中型免許は特に免許経歴が必要なく、18歳以上で取得が可能です。実際に免許を取得する際は適性試験が行われます。適性試験では視力や深視力、色彩識別能力、聴力、運動能力などのチェックが行われ、基準を満たしていないと免許の取得はできません。
視力の合格基準は両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上です。深視力は三桿法の奥行知覚検査器を使って2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下である必要があります。色彩識別能力は赤・青・黄の識別ができること、聴力は両耳の聴力が10メートルの距離で90デシベルの警音器が聞こえることが基準です。ただし、聴力は特定後写鏡(ワイドミラー又は補助ミラー)などを取り付け、聴覚障害者標識を表示すれば、条件に該当していなくても免許を取得できます。*4
準中型免許取得の流れ
準中型免許を取得する方法としては、主に一発試験と指定自動車教習所に通う方法があります。
一発試験は、運転免許センターや運転試験場で直接試験を受けて合格を目指す方法です。費用を削れるメリットがあるものの、難易度が高いためあまりおすすめではありませんが、流れは以下の通りです。
- 運転免許センターまたは運転試験場で仮免許の学科試験と技能試験を受ける
- 仮免許交付
- 定められた時間の路上練習を行う
- 本免許の学科試験・適性試験・技能試験を受ける
- 取得時講習を受ける
- 免許証交付
指定自動車教習所に通って卒業検定を受ける方法では、所定の教習をすべて終えれば自動車教習所で卒業検定を受けられるため、運転免許センターでの実技試験が免除されます。
- 入学後、適性試験と学科講習、技能講習を受ける(普通免許・二輪免許を保有していれば学科講習は免除)
- コース内で修了検定を受ける
- 仮免許の学科試験を受ける
- 仮免許証交付
- 学科講習と路上での技能講習を受ける
- 卒業検定を受ける
- 運転免許センターまたは運転試験場で学科試験と適性試験を受ける
- 免許証交付
準中型免許の制度が導入される前に普通免許を取得した人は、限定解除で準中型免許の取得が可能です。限定解除については、次の段落で詳しく説明します。
準中型の限定解除とは?
準中型免許の新設以降、準中型免許で運転できる車両総重量は7.5トン未満になりました。しかし、準中型免許が導入される前、2007年6月2日から2017年3月11日の間に普通免許を取得していた人の場合、準中型自動車については車両総重量5トンまで運転できる「5トン限定準中型免許」になっています。この限定を解除すれば、限定なしの準中型免許にすることが可能です。
準中型の限定解除は「一発試験に合格する」、「自動車教習所の技能試験を受講して卒業する」の2種類の方法があります。一発試験は運転免許センターまたは運転試験場で実技の試験を受け、合格すれば手数料の支払いを行ったうえで限定解除の審査を受ける方法です。ただ運転できればいいのではなく、安全確認を含めて厳しく評価されるため、何度か挑戦することを念頭に置いたほうがいいでしょう。自動車教習所で技能講習を受講する方法では、講習を受けて試験に合格すれば、あとは運転免許センターで適性検査と手数料を支払い、限定解除の手続きを行うだけです。
2007年に新設の中型免許
2007年に中型免許が導入される前、交通死亡事故のなかでも貨物自動車による発生率が高い状況でした。背景として道路交通法が制定された1960年当時に比べると、貨物自動車の大型化が進んだことが考えられています。特に事故が多かったのは普通免許の上限に近い5〜8トンの車両や、大型自動車でも特に大きい11トン以上の層で死亡事故件数が高くなっていたのです。
対策を施してもなかなか改善せず、知識や技能の不足が原因で起こる事故を抑止するために普通免許と大型免許の間に新しい区分が設けられました。
中型免許で乗れる車両は?
中型免許で乗れるのは車両総重量7.5トン以上11トン未満、最大積載量4.5トン以上6.5トン未満、乗車定員が11人以上29人以下の車両です*1。国内の商用車メーカー各社では中型免許で運転できる車両を販売しており、さまざまな配送業務で使われています。
また、クレーンを装備したユニック車やミキサー車、自動車を運搬する積載車なども大きさによっては運転が可能です。引っ越し業界では、ファミリー向けにより多くの荷物を積載できる4トントラックが中型免許で運転できます。さらに乗車定員が29人以下のマイクロバスも運転できます。マイクロバスについては、別に詳しく解説します。
中型免許の受験資格は?
中型免許の受験資格は20歳以上、普通免許または準中型免許、大型特殊免許のいずれかを取得したうえで、経歴が通算2年以上あることです。ただし、2022年5月13日の改正道路交通法によって受験資格が緩和されました。これにより中型免許は「受験資格特例教習(座学7時間以上と技能29時間以上の合計36時間以上)」を修了した19歳以上で、かつ、普通免許の保有歴が1年以上あれば受験が可能になっています。*5
適性試験では準中型免許と同様に視力の合格基準が両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、赤・青・黄の色彩識別能力があることも求められます。深視力は三桿法の奥行知覚検査器を使って2.5メートルの距離で3回検査した平均誤差が2センチメートル以下、聴力は両耳の聴力が10メートルの距離で90デシベルの警音器が聞こえることが基準です。
中型免許取得の流れ
中型免許の取得方法も、主に一発試験と指定教習所に通う2つの方法があるほか、手持ちの普通自動車免許の取得時期によっては限定解除をする方法もあります。
一発試験は、運転免許センターまたは運転試験場で直接技能試験を受けます。準中型免許と同様に難易度が高い方法です。
- 適性試験と仮免許試験を受ける
- 5日間以上の路上練習を行う
- 運転免許センターまたは運転試験場で適性試験と技能試験を受ける
- 合格後に取得時講習・応急救護講習を受ける
- 免許証交付
指定自動車教習所に通って免許を取得する方法は一発試験に比べると費用がかかるものの、本試験の技能試験が免除されるためおすすめです。
- 指定自動車教習所で学科教習と技能教習を受ける
- 卒業検定に合格する
- 運転免許センターまたは運転試験場で適性試験を受ける(技能試験は免除)
- 免許証交付
2007年6月1日以前に普通免許を取得し、8トン限定の中型免許を所持している人は、限定解除をすれば限定なしの中型免許が取得可能です。詳細は後述します。
マイクロバスを運転するには中型免許がマスト!
乗車定員が11人以上29人以下の車両が運転できる中型免許はマイクロバスの運転もできるため、持っていれば物流業界以外でも活かせるシーンがあります。自動車教習所の生徒や商業施設の利用者などを乗せる送迎バスも、多くはマイクロバスです。ほかにもゴルフ場や健康ランド、ホテルや結婚式場、飲食店から病院まで、マイクロバスは実にさまざまな場所で活用されています。
幼稚園の園児を送迎するバスや、少年野球チームなどが遠征するときによく使われているのもマイクロバスです。企業でも社員の送迎用にマイクロバスを使っているところがあるほど、使い勝手のいい車両です。ただし、中型免許でも2007年6月1日以前に普通免許を取得した8トン限定の中型免許や準中型免許は乗車定員10人以下の車両に限られるため、マイクロバスの運転はできません。
2007年6月1日以前の運転免許なら限定解除で取得可能
2007年6月1日以前に普通免許を取得している場合、その免許は「8トン限定中型免許(旧普通自動車免許)」と呼ばれる免許になっています。8トン限定中型免許で運転できる車両の範囲は、車両総重量が8トン未満、最大積載量が5トン未満、乗車定員は10人以下です。8トン限定中型免許では、限定なしの中型免許に比べると運転できる車両の範囲が狭くなります。ただし、8トン限定中型免許を保有している人の場合、限定解除の手続きをすれば一から中型免許を取得するよりも短い時間で中型免許を取得できます。
限定解除の方法にも、主に一発試験を受ける方法と自動車教習所に通う方法があります。一発試験では運転免許センターや運転免許試験場に直接赴き、技能試験に合格すると解除が可能です。自動車教習所に通う方法は、所定の時間の技能教習を受講し技能審査に合格したのち、運転免許センターなどで免許変更の手続きを行うというものです。
運転免許の最上位資格!大型免許
先述のように大型免許を取得していれば普通自動車から大型自動車まで幅広い種類のトラックを運転でき、運転免許の最上位資格として運輸業界では重宝されています。
実際にトラックドライバーとして就業することを目的に大型免許を取得する場合、条件を満たしていれば助成金や補助金の対象になることがあります。また、中型免許を持っていると教習時間が少ないため、免許取得のための時間や費用をおさえることが可能です。
大型免許で乗れる車両は?
大型免許は車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上の車両が運転できます。もちろん、それよりも小さい中型自動車や準中型自動車、普通自動車の運転も可能です。大型免許で乗れるのは長距離を走行するような大型の貨物自動車のほか、ダンプカーやミキサー車など、さまざまな車両があります。
大型の貨物自動車を運転するための大型免許は、正確には「大型自動車第一種免許」といいます。同じ大型車両でも観光バスや路線バスなど旅客を乗せて運転するためには、「大型自動車第二種免許」を持っていなければなりません。また、ホイールローダーやブルドーザーなど現場作業で活躍する大型特殊自動車は大型特殊免許、トレーラーはけん引免許が必要です。また、タンクローリー車のように危険物を運搬する場合は、危険物取扱者など別の資格が必要になる場合もあります。
大型免許の受験資格は?
大型免許を取得するための受験資格は年齢が21歳、普通免許または準中型免許、中型免許、大型特殊免許のいずれかを取得し、経歴が通算3年以上あることです。ただし、大型免許も中型免許と同じように2022年に施行された改正道路交通法により、「受験資格特例教習」を受講すると免許経験が1年以上あれば最速19歳で取得できるようになりました。*5
また、大型免許もほかの免許と同じように適性試験を受ける必要があります。大型免許は中型免許と基準が同じで、視力は両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上です。深視力も三棹法の奥行知覚検査器を使って3回2.5メートルの距離で検査を行い、平均誤差が2センチメートル以下であることが求められます。
赤・青・黄色の識別ができる色彩識別能力と、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえる両耳の聴力(補聴器可)も必要です。
大型免許取得の流れ
大型免許の取得も主に一発試験と指定自動車教習所に通う2通りの方法があります。
一発試験は仮免許試験や本試験の手数料、合格した際の取得時講習の受講料などがかかりますが、自動車教習所に通う場合に比べると費用をおさえることが可能です。しかし、一般的に一発試験での合格は難易度が高く、路上練習の車両や同乗してくれる人を探す必要もあります。
- 適性試験と仮免許試験を受ける
- 5日以上の路上練習を行う
- 運転免許センターまたは運転試験場で本試験を受ける
- 合格後に取得時講習・応急救護講習などを受ける
- 免許証交付
自動車教習所に通う方法は費用がかかりますが、本試験での技能試験が免除になります。一発試験よりも合格しやすく、おすすめの方法です。
- 指定自動車教習所で学科教習と技能教習を受ける
- 卒業検定に合格する
- 運転免許センターまたは運転試験場で適性試験を受ける(技能試験は免除)
- 免許証交付
トラックドライバーの免許の種類はさまざま
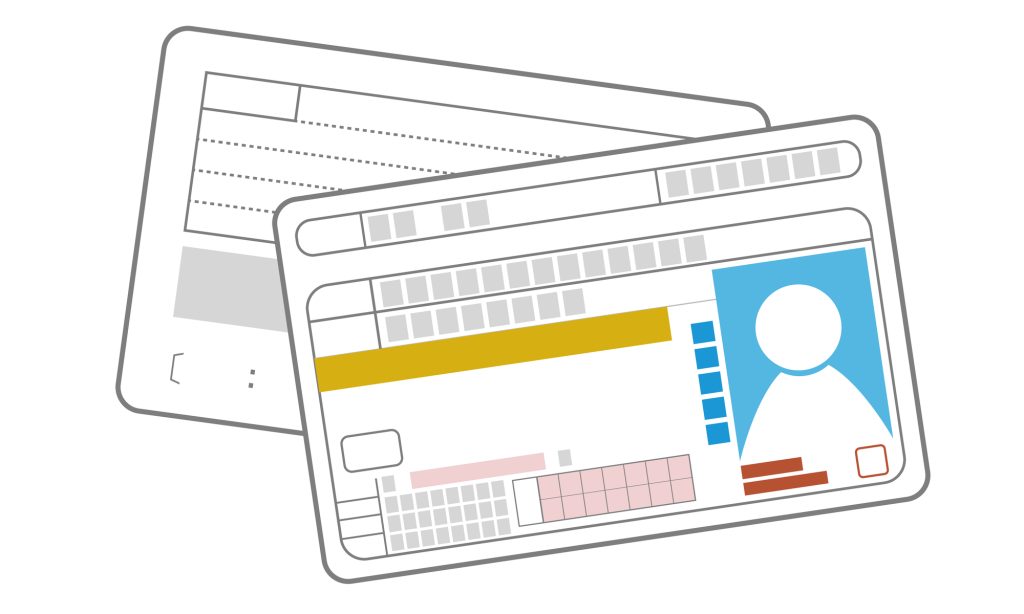
自動車を運転するための免許には普通免許から大型免許まで、さまざまな種類があります。もともとは普通免許と大型免許の2つの区分しかありませんでしたが、運送業界の人材不足解消や交通事故削減を目的に2007年に中型免許、2017年に準中型免許が新設されました。
普通免許でもトラックドライバーとして運転できる車両がありますが、より大型の車両を運転できる準中型免許や中型免許、大型免許を取得すれば、さらに活躍できるシーンは広がるでしょう。将来なりたい職業を見据えながら、免許の取得を検討してみてください。
文責:働きやすい職場のミカタ編集部
*1
出所)
大阪府警「免許の種類と運転できる自動車など」
URL:https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/untenmenkyo/3/5969.html
*2
出所)岐阜県公式ホームページ(運転免許課)「運転免許の種類と運転可能な車両 」
URL:https://www.pref.gifu.lg.jp/page/100855.html
*3
出所)警視庁「準中型自動車・準中型免許の新設について」
URL:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/chugata.html
*4
出所)徳島県警「聴覚に障害がある方の運転免許取得等について」
URL:https://www.police.pref.tokushima.jp/06menkyo/0621-tyoukaku/index.html
*5
出所)
新潟県警「運転免許受験の案内(受験資格、必要書類等)」
URL:https://www.pref.niigata.lg.jp/site/kenkei/menkyo-siken-sikaku-sikaku.html
